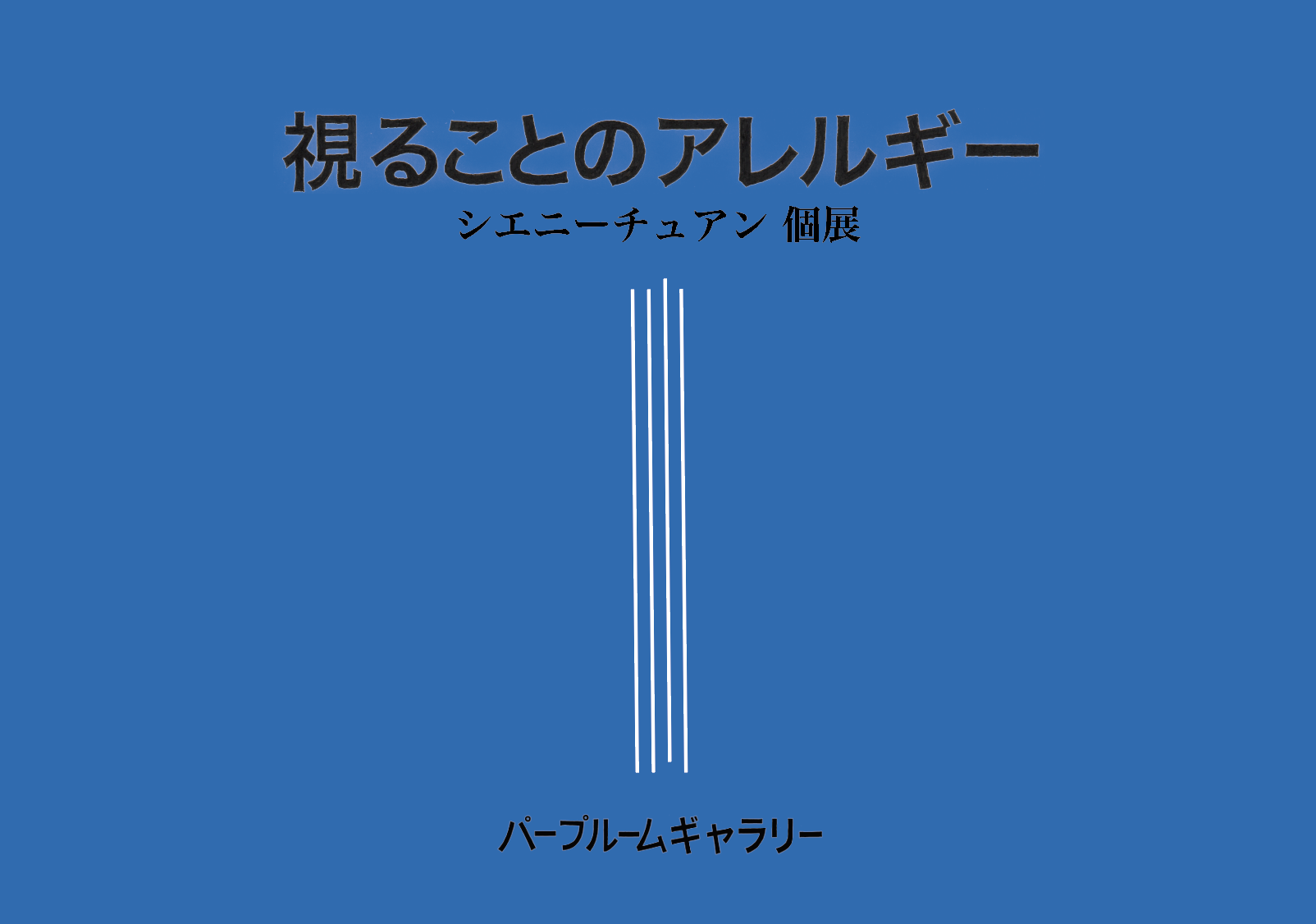
視ることのアレルギー
Allergy of Seeing
- 会期|
- 2021.9.29-10.9(水曜日は休廊、ただし初日29日は開廊)
- 時間|
- 15:00-20:00
- 場所|
- パープルームギャラリー、みどり寿司
- 企画|
- パープルーム
- 協力|
- パープルーム予備校

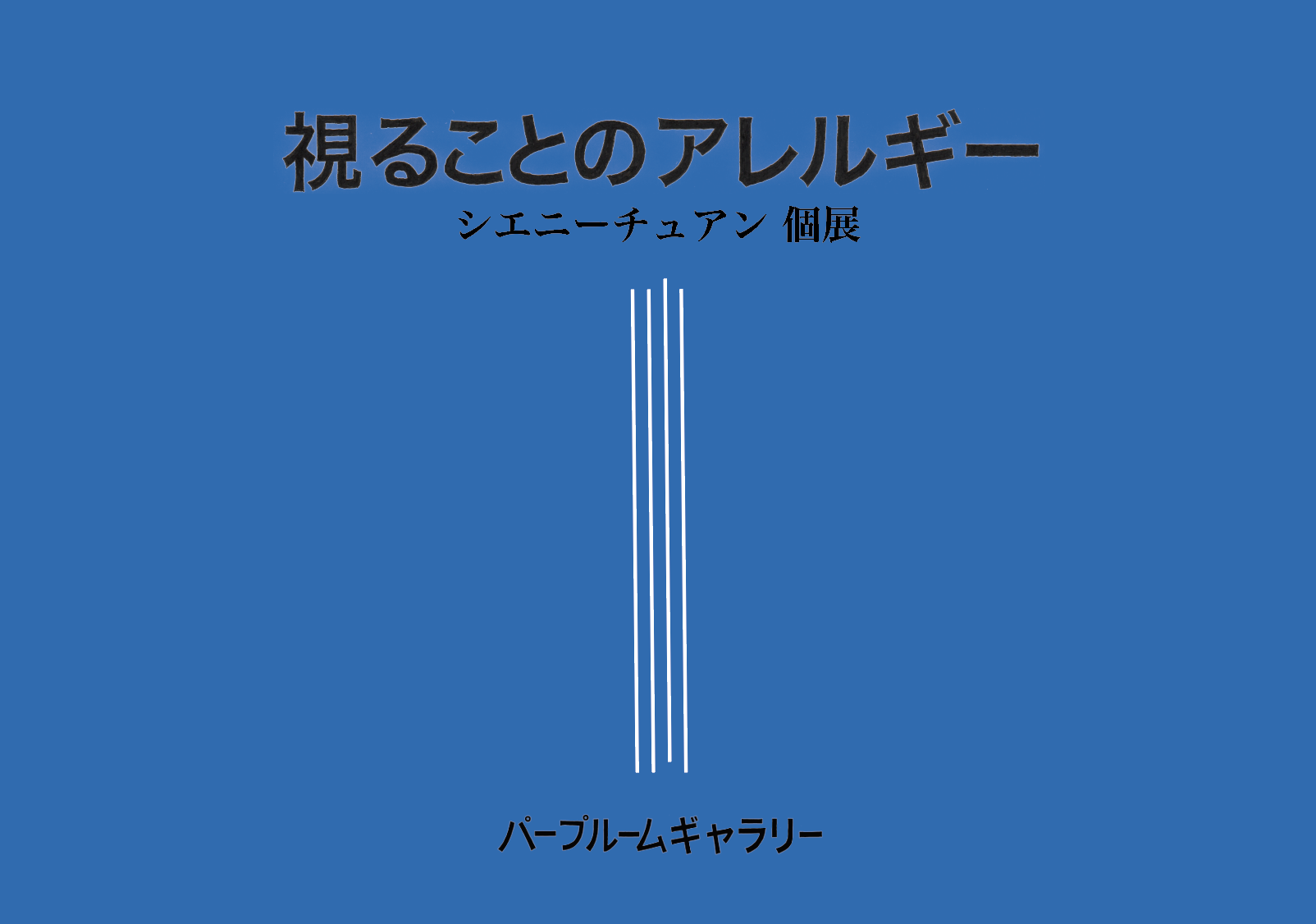
「絵画とはなにか?」そんなシンプルな問いに即答することは案外、難しい。
絵画を語る上でなにを前提とするかによって、おのずと見える風景や射程は変わってくる。それは絵画に限らずあらゆるものがそうだと言える。けれども、絵画を考えることがとりわけ難しいのにはいくつか理由がある。それは絵画が今日まで世界中で描かれ幾度も定義し直されている上に、近年では絵画の価値を担保してきた美術史がかつてのように機能しなくなってきた。そして新しい価値の提案もままならないという批評の貧困さが暗い影を落としている。さらに最近ではアートマーケットが急速に拡大し作品が売れることが作家の評価そのものと認識されるケースも少なくない。インスタグラムには描かれたばかりの新作絵画が無数に蔓延っており、それらの多くは絵画の言説とは無関係に制作され消費者の欲望を満たしていく。つまり現在の絵画の一部は批評を重んじず、たんに「映え」を追求し人々のライトな欲望に応える商業主義に最適化したコンテンツということになる。
いや、本当にそうだろうか?ある程度は前述した通りかもしれない。しかし、そうとも言い切れない側面が絵画にはあるように思う。巨匠と言われる先行世代の画家たちの多くはある特定の国やコミュニティに属している。彼らの残した仕事の多くが豊穣であることは疑いがないだろう。けれども印象派にしろ、抽象表現主義にしろ、〇〇にしろ、原理的にあるいは技術的に高度で容易には乗り越え難い素晴らしい達成ばかりかというと疑問が残る。画家の才能や功績は人為的に作られた設定に過ぎず、実はどんな人物がどの時代にどの場所・コミュニティにいたのかということの方が「個の創造」よりも比重が大きいのかもしれない。
さらに批評を司っている有識者がいくら聡明で優秀であろうとも、彼らが所属する大学や専門機関の内部の序列や政治と密接に関わっている以上、観測範囲や交友関係はその場の持つ性質にある程度規定されてしまう。世界中で無数に生み出され続ける絵画は当然のことながら美術大学を卒業した作家や美術業界と近い距離にいる作家以外の手によるものも含まれる。しかし、美術界に登場する作家たちの多くはインサイド側である。現在の日本でも学閥の壁は高く、知らず知らずのうちに作品の内容とは無関係の選別が起こっているのが現状ではないだろうか。
絵画の制作の現場における興味深い「達成」は作家の出自や所属に関係なくいたる所で確認できる。しかしそのほとんどは人目に触れることも批評されることもない。一握りのエリートの才能のみが突出しているかのように思われがちな美術の世界のあり方、それを後押しする批評空間の狭さ・欠陥を今後どのように改善し、絵画と批評の新しい関係を構築し得るのか。それはたやすいことではないし、不可能なことなのかもしれない。しかし自戒を込めて言えば、わたしたちはこの不均衡さこそが美術であると居直らないために努力し、策を講じ続けなくてはならない。
さて、シエニーチュアン個展「視ることのアレルギー」はこのような現状の認識を前提とし、具体的な実践として企画された展覧会である。シエニーチュアンはこれまでパープルームギャラリーを共に運営してきたパープルームの中心メンバーでもある。さらに、これまでに23冊もの弊廊の展覧会冊子を共に作ってきた。そんな運営や企画に携わってきたシエニーチュアンが画家としての本格的なスタートを切るのが本展である。この場ではシエニーチュアンの作品の具体的な紹介は差し控えようと思うが、本展が絵画作品の価値を保証し、強化し、印象操作する役割を担う「批評」と「絵画」との新しい関係を取り持つ機会になれば幸いである。ちなみに本展に展示される作品は昨今のアートマーケットの現状を鑑みて原則的に非売とする。
梅津庸一(美術家・パープルーム主宰)
「私はだれかのみてきた幻想が好きだった。」
こんなこと誰にも言いたくなかったが、私が絵画や美術を思考する過程でやっぱりどうしても語っておかなければならない感覚がある。ずいぶん昔から付き合ってきた疾患の事である。気づくと私の目の前にはショッキングピンクの鮮やかな色面が迫り立っている。
私の目と鼻の先にひっついたまま上下左右どこまでも延々と広がっている。壁面に見えるがそうではない。私はその全貌をみたことがないのにも関わらずそれが地球なんかよりも大きな「丸」のほんの一部だということを知っている。とたんに手に何か握っている感覚とこの丸を一人でなんとかしなくてはいけないという強迫観念、同時にどうすることもできないという諦めにも似た戸惑いを引き起こし、どの言葉も陳腐に聞こえるほどの恐怖を私に与える。自分がはなから存在していないような、怖くて、情けなくて、一生の短ささえ感じる。しかしそれは絶大で目が離せないほどにとても魅力的だった。いや、魅力的という言葉では包括しきれない。なんともうまく説明しづらくて困るのだが、それがこれまで私が見て認識してきた絵画史と美術というものの総体となぜかとても似ている気がするのだ。
私はその幻覚と同様の希望と絶望を美術に対して抱いている。それはもう正気じゃいられない。気が狂いそうだ!制作の際の、前後にある膨大な何かと繋がってしまったような感覚はいつも私をそのような気持ちにさせる。それは何かを描くという行為自体に起こる、世の中すべての天則的な秩序と身体的な小さな個の行為の想像力が呼応する制作行為の重要なポイントである。私の絵画に定着するものなんて私が考えうる最小単位の応答にすぎない。
これを内向的な精神の話へと片付けてしまうこともできるが、そうしてしまえば絵画ないし美術自体の価値を規定することも不可能のように思う。そもそも考えてみれば私たちが観測できる範囲など膨大な美術の手前のほんの小さな針先にすぎないし、それこそ誰かが利己的に見た幻覚や政治の幻想の光芒にすぎないのかもしれない。
しかしそれでも私は制作を通してその強迫観念に基底する、美術の鮮やかな希望と絶望の渦中に自らを投げ込んでも、どうしてもここにいたいのである。
私はだれかのみてきた幻想が好きだった。
シエニーチュアン
シエニーチュアン Shieneychuan
1994年生まれ、愛知県出身。
2018年にパープルームに加入。